
通信距離が長く遠い場所にあるRFIDタグも読み取れるRFID(UHF帯)は、棚卸し業務や備品管理など、さまざまな場所で活用されています。
RFIDを使用する際に注意したいのは、RFIDタグ(ICタグ)を用意するだけでは使えないという点です。RFIDタグ内のデータを読み取るためにはRFIDリーダーやリーダライタと呼ばれる端末とデータを処理するシステムが必要です。
またRFIDで使用する周波数帯にもいくつかの種類があるため、現場の環境に合わせた機器の選定が必要です。現場に適切なRFIDを導入するためにはデータを読み取る仕組みのほか、種類ごとの違いを知っておく必要があります。
本記事では、RFIDリーダーの仕組みや種類などをご紹介します。
目次
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
1.RFIDリーダーの仕組み(UHF帯)
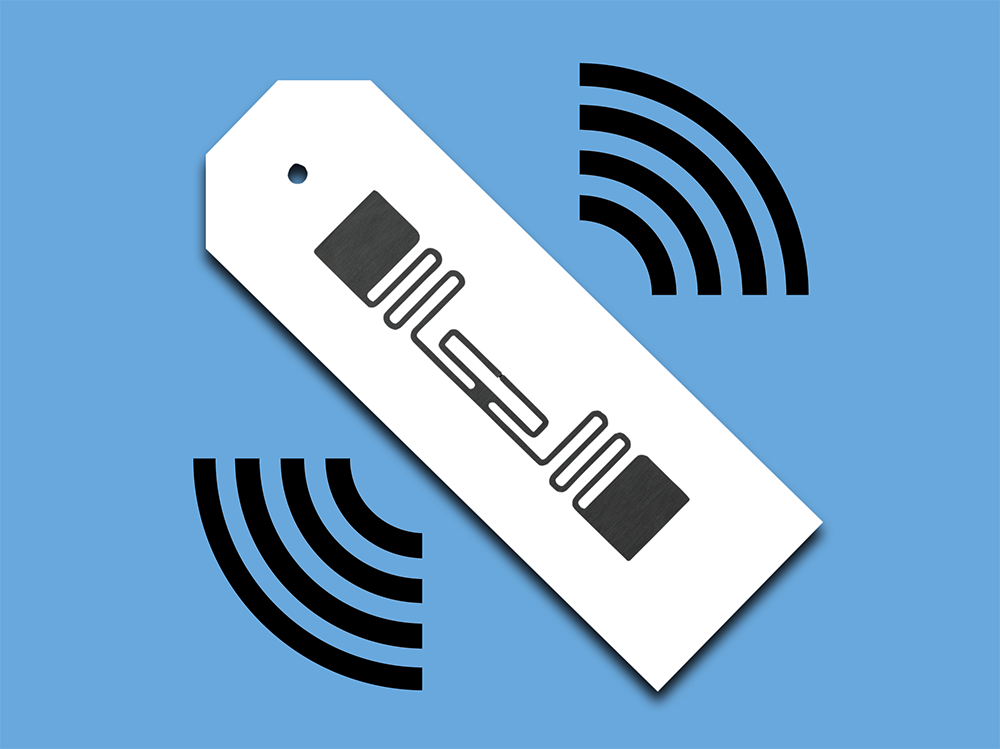
RFIDシステムは、RFIDタグ内のデータを読み取るために電波を利用します。電波を送受信したり、出力を制御したりする機器がRFIDリーダーです。
RFIDリーダーに搭載されたアンテナが電波の送受信を行い、制御部が電波を出したり止めたりするタイミングと出力の制御を行います。
一方で、データの読み取りだけではなくRFIDタグ内にデータの書き込みもできる機器は、リーダライタと呼ばれます。一般的にはRFIDタグ内のデータを読み取る用途で使われることが多いため「リーダライタ」も「リーダー」と呼ばれることが多いですが、厳密には異なる機器です。
機器の導入時には、読み取り専用のリーダーなのか、書き込みも行えるリーダライタなのかを確認しておくことが重要です。
電波出力の設定
RFIDリーダーの通信距離は、通信方式やアンテナの性能やICタグの大きさなどさまざまな要素によって変化します。そのうちの一つが電波出力です。
電波出力が大きければ大きいほど読み取りできる距離が長くなります。併せて電波の照射範囲が広がるため読み取れる範囲も広がります。
一方、電波出力が小さくなればその分読み取りできる距離が短くなり、読み取れる範囲も狭くなります。
電波出力は大きければよいというわけではなく、RFIDタグの使用目的によって設定することが大切です。
例えば、セルフレジで使用するRFIDリーダーの電波出力を大きくすると、お客さまが手に持っていない周囲の商品まで読み取ってしまう可能性があります。そのため、商品タグを読み込むセルフレジやRFIDタグにデータを書き込む場合にはRFIDリーダーの電波出力を小さく設定して他のタグへの干渉を防ぐ調整が必要です。
偏波特性
RFIDリーダーの読み取り範囲は、アンテナの大きさや電波出力の大きさだけでなく、電波をどのように照射するかという偏波特性によっても変化します。
RFIDリーダーのアンテナから照射される電波は“円偏波”と“直線波”という2つの偏波に分けられます。
【円偏波】
- 電波がらせん状に照射される
- 読み取り距離が短い
- 読み取り範囲が広い
【直線波】
- 電波がまっすぐ照射される
- 読み取り距離が長い
- 読み取り範囲が狭い
円偏波のRFIDリーダーは、読み取り範囲が広いという特徴を生かしてアパレルショップの棚卸しや製造現場の製品管理、医療現場の精密機器管理などで多く利用されています。
一方、直線波のRFIDリーダーは、読み取り距離の長さを活かして建設業の資材管理や製造業における大型製造機械のメンテナンス管理などで活用されています。
2.RFIDリーダーとリーダライタの種類

RFIDリーダーとリーダライタ(本項と次項では便宜上、この2つを合わせてRFIDリーダーと呼称します)は、形状や設置方法から大きく3つの種類に分類されます。
- ハンディ型
- 卓上型
- 固定型
種類ごとに適した用途や活用方法が異なりますので、それぞれの特徴を確認しておきましょう。
ハンディ型
手に持ってRFIDタグを読み取るタイプのRFIDリーダーがハンディ型です。ハンディ型のRFIDリーダーはさらにいくつかの種類に分けられます。
例えば、データ処理端末とリーダーが一体化していてデータ読み取りからデータ処理まで1台で行えるタイプや、Bluetooth接続でパソコンやスマートフォンなど別の端末とペアリングして使用するセパレート型が代表的です。リーダー上部にペアリングした端末を取り付けられるライドオン型もあります。
また、ハンディ型のRFIDリーダーの形状は他のハンディターミナルと同じく、ガンタイプやスティックタイプが大半で、すでに普及しているバーコードスキャナーと同様に操作できるため、現場への導入がスムーズに進むこともメリットだといえます。
片手で操作できるため、RFIDタグを読み取る対象物が動かせない倉庫での棚卸しや在庫の探索などに活用できます。
卓上型
テーブルや任意の場所に設置してRFIDタグのデータを読み取るタイプが卓上型です。読み取りの際に手元で何か特別な操作をする必要がないので、ハンズフリーで読み取りを行うことが可能です。
アンテナ上だけを読み取れるなど高精度なタイプもあります。
ただし、設置するためのスペースの確保や給電が必要となります。
卓上型はハンズフリーで使えるため、店舗のレジ決済や持ち出し管理の記録といったシーンに適しています。生産ラインなど自動で読み取りを行いたい現場にも適しているでしょう。
固定型
天井や壁、床などに設置して使用するタイプが固定型で、エリア内を通過したRFIDタグの読み取りを行います。
例えば、ゲート型のRFIDリーダーを現場の出入り口に設置すれば、入出庫時に自動で商品の数量を読み取ったり人の出入りを把握するといったことが可能です。
ワゴンやカゴなどで商品を運びながらゲートを通すだけで一括読み取りが可能なため、物流業界の入出荷検品でよく利用されています。その他には、図書館の蔵書管理システムや店舗の万引き防止用としても活用されています。
固定型は大きく、制御部とアンテナが一体になっているタイプとアンテナが独立しているタイプに分けられます。アンテナが独立しているタイプはそれぞれの設置場所を柔軟に変更できるため、特定エリアに限定した読み取りができる点が特徴です。
ただし、固定型はハンディ型や卓上型に比べて設置の手間がかかりやすい傾向にある点には留意する必要があります。
サトーのRFID機器(リーダー)の詳細については以下をご確認ください。
なお、RFIDリーダーは、使用する周波数帯でも種類が分かれます。RFIDの周波数ごとの違いについてはこちらの記事で解説しています。
関連記事
3.RFIDの導入事例
ここからは、サトーのRFIDソリューションを導入した企業の事例をご紹介します。
現場にRFIDの導入を検討する際の参考にしてください。
RFIDの導入により生産計画変更および出荷遅延ゼロを実現

大手ベアリングメーカーであるNTN株式会社様は、自動車業界の環境変化により大量生産から多品種少量生産へのシフトに取り組んでいました。
多様な市場ニーズに対応するには、製品を出荷する鉄かごやパレットなどのリターナブル容器の確保が必須です。
しかし容器の所在管理が難しく、生産計画や物流に悪影響を与えていました。
同社は問題解決に向けてサトーのRFIDソリューションを導入し、リターナブル容器の所在を可視化することで一元管理を行うプロジェクトに取り組みました。その結果、生産計画変更および出荷遅延ゼロを実現しています。
【導入前の課題】
- 容器の所在不明が原因の生産計画の遅延・変更などの悪影響が年5回程度発生
- 「容器を探す」「製品積み替え」「品番変更」などイレギュラー業務が発生
- 容器の追加購入や臨時便輸送により年間300万円程度のコストが発生
【導入による効果】
- 生産計画の変更や出荷遅延ゼロを実現
- イレギュラー作業が減少し、スムーズな生産計画や円滑な出荷を実現
- 容器の追加購入や臨時配送などのコスト
具体的な事例内容については以下もご確認ください。
関連記事
-

RFIDリーダーもスマホ連携型が主流?スマホ機能を搭載したRFIDリーダーを活用するメリットとは
RFIDリーダーにもスマホ形状のものや、スマホ向けのOS、もしくはスマホ機能を搭載した商品が増えていますが、どのようなメリットがあるのでしょうか。
ここでは、スマホ連携型RFIDリーダーの特徴や、スマホ機能を搭載したRFIDリーダーを活用するメリットなどをご紹介します。
4.RFIDリーダーは用途に適した種類を選ぶことが重要
RFIDを活用すれば在庫管理や棚卸しなどが効率化できます。
ただしリーダーには多くの種類があり、それぞれ適した環境や用途が異なります。導入を検討する際はリーダーの種類と特徴を理解することが重要です。
現場の課題解決に向けてRFIDの導入を検討している場合は、サトーへお気軽にご相談ください。多くの導入実績から得た知見で現場の課題解決策をご提案します。
関連コンテンツ
商品やソリューションについてのお問い合わせ
お客さまヘルプデスク24時間365日

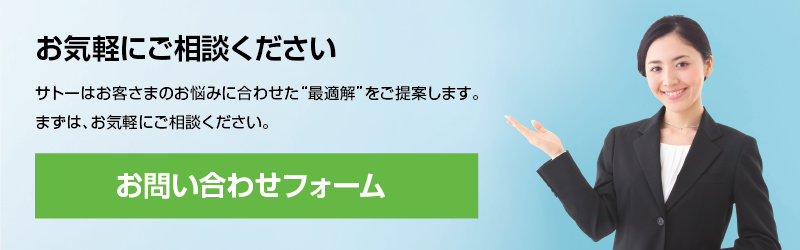











 サトークイックオーダー
サトークイックオーダー