
HACCP(ハサップ)は、食品の製造・加工・流通における衛生管理を体系的に行うための国際的な手法です。
日本では、改正食品衛生法の施行により、原則として全ての食品関連事業者に対してHACCPの導入が義務付けられました。
本コラムでは、食品事業者が知っておくべきHACCPの基本知識や実施のステップ、HACCP対応に役立つ仕組みの導入事例など食品の衛生管理に役立つ情報を解説します。
目次
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
1.HACCPとは?食品衛生管理の基本

HACCPは、食品事業者が衛生管理を体系的に行うための国際的な手法です。
原材料の入荷から製品の出荷までの各工程において、食中毒菌による汚染や異物混入などの危害要因を、科学的根拠に基づいて管理することができます。
HACCPは、“HA(Hazard Analysis:危害要因分析)”と“CCP(Critical Control Point:重要管理点)”の2つの要素で構成されています。
HAの目的は、食中毒以外にも化学物質や金属を含む異物など、健康被害につながる危害要因を排除・低減する管理方法を明らかにすることです。
一方、CCPはHAに基づき健康を損なわないレベルに危害要因を排除・低減するために加熱や冷却、包装など特に重要な加工工程の管理を行います。
HACCPに取り組むことによって企業が期待できる主なメリットは以下の通りです。
- 品質のバラつきの減少
- クレームやロス率の低下
- 現場の状況把握の効率化
- 食の安心・安全の確保
- 従業員の衛生に対する意識向上
2.従来の衛生管理方法との違い

HACCPは従来の衛生管理方法と比較して、より明確な危害要因の把握と重点的な管理が可能です。
従来、食品製造の工程間においては、抜き取り検査(モニタリング検査)を実施することが一般的でした。
HACCPでは危害要因を予測・分析した上で重要度の高い工程や手順を優先的に管理することにより、食品の安全性を証明する必要があります。
これにより、抜き取り検査に比べて問題のある食品の出荷を未然に防ぎやすくなる他、原因の追及を容易に行えるようになります。
3.2020年よりHACCPが制度化

2018年の食品衛生法の改正に伴い、2020年にHACCPに則した衛生管理が義務化されました。1年間の猶予期間が設けられ、2021年6月からは完全制度化されています。したがって、全ての事業者がHACCPに沿った衛生管理に対応しなくてはなりません。
HACCPの取り組み自体は、1990年代から日本でも行われていましたが、中小企業への普及が進んでいませんでした。そのため、HACCPの制度化は大きな契機といえます。
出典:厚生労働省「HACCP(ハサップ)」
4.HACCP制度の区分と対象事業者

HACCP制度は大きく2つの区分に分けられ、それぞれ対象事業者が異なる点が特徴です。ここでは、区分ごとにどのような事業者が対象となっているのかをご紹介します。
HACCPに基づく衛生管理(旧基準A)
厚生労働省「HACCPに基づく衛生管理」においては一般的な衛生管理に加え、コーデックス委員会で定められたHACCPの7原則に基づいた衛生管理が求められます。
具体的な実施事項は以下の通りです。
- 衛生管理計画の作成
- 周知の徹底
- 必要に応じた手順書の作成
- 実施状況の記録
- 衛生管理計画及び定期的な手順書の効果検証と見直し
対象事業者には大規模事業者と畜場、食鳥処理場が含まれます。
出典:厚生労働省「HACCPに基づく衛生管理」
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(旧基準B)
個人経営の飲食店をはじめ小規模事業者は、人的な問題からHACCPに基づく衛生管理に対応できないケースも考えられます。
そのような場合は各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化したアプローチによる衛生管理を行うことでHACCPに沿っているとみなされます。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の対象事業者は以下の通りです。
- 小規模事業者(食品などの取り扱いに携わる者の数が50人未満)
- 該当店舗での小売販売を目的とした製造・加工事業
- 飲食店営業や喫茶店営業を行う者、その他の食品を調理する事業者(そうざい製造やパン製造業など)
- 容器包装に入れられた食品のみを貯蔵や運搬、販売する事業者
- 食品を分割して容器包装に入れたり、包んで小売販売する事業者(八百屋やコーヒーの量り売りなど)
工場や飲食店におけるHACCPに基づいた衛生管理のポイントについては、以下の記事も併せてご確認ください。
HACCP対象外の事業者
原則として全ての食品等事業者がHACCPの対象になりますが、一部対象外の事業者もあります。対象外の事業者は以下のとおりです。
- 農業及び水産業における食品の採取業
- 食品や添加物の輸入業者
- 食品や添加物の貯蔵または運搬のみ行う営業(食品の冷凍や冷蔵業を営む場合は除く)
- 常温で長期間保存しても、腐敗や変敗、品質の劣化による食品衛生上の危害が発生するおそれがない包装食品の販売
- 器具・容器包装の輸入または販売
- 学校や病院以外の給食施設で、1回の提供食数が20食程度未満の施設
5.HACCPを遵守しないと罰則はある?

HACCPの制度は食品衛生法に基づいて義務化されている一方、HACCPそのものに対する直接的な罰則は規定されていません。
HACCPの要件に不備がある場合は、口頭や文書で改善措置などの行政指導が行われます。行政指導による効果が見られない場合は、営業の禁止や停止といった行政処分が下される可能性もあるため注意が必要です。
6.HACCPを実施するための「7原則12手順」

HACCPに沿った衛生管理を適切に実施するためには、コーデックス委員会が定める「7原則」を要件とすることが重要です。ここでは、7原則を遂行するための手順をご紹介します。
原則を進めるにあたっての準備(手順1~5)
-
手順1HACCPチームの編成
製品に関する情報を収集するために、関連部門や社外の専門家などから業務に精通した担当者を集める
-
手順2製品説明書の作成
製品の名称や種類、原材料などを全て洗い出す
-
手順3製品の用途と対象者を確認
加熱の有無、誰が食べるのかなど、製品の特性を確認する
-
手順4製造工程図(フローダイアグラム)の作成
原材料の仕入れから製品の出荷までの流れを書き出しておく
-
手順5製造工程図の現場確認
手順4で作成した工程図を現場で確認して、修正が必要な場合は対応する
ここまでが、HACCPの7原則を進めるにあたっての準備です。
HACCPの7原則(手順6~12)
次に、以下の手順に沿って7原則を実施します。
-
手順6(原則1)HA(危害要因分析)の実施
工程ごとに危害要因になる可能性があるものを洗い出して対処方法を検討する
-
手順7(原則2)CCP(重要管理点)の決定
加熱・殺菌など、危害要因を取り除くための重要管理点を決定する
-
手順8(原則3)CL(Critical Limit:管理基準)の設定
手順7で決めた重要管理点の基準を決定する
-
手順9(原則4)モニタリング方法の設定
重要管理点が現場で適切に実施されているかを確認するためにモニタリング方法を決定する
-
手順10(原則5)改善措置の設定
管理基準を満たしていない場合どのような改善措置を行うべきかを決定する
-
手順11(原則6)検証方法の設定
衛生管理が手順通りに進み、有効に機能しているかを検証する方法を決定する
-
手順12(原則7)記録と保存方法の設定
管理状況を記録して、どのように保存するかを定める
なお、HACCPにおける温度管理および文書についての詳細は以下の記事をご参照ください。
-

HACCPにおける温度管理の重要性。具体的な管理方法のポイントは?
本コラムでは、食品の温度管理の重要性とデジタル化を成功させた導入事例についてご紹介しています。
7.HACCPの認証取得も有効
HACCPは制度として義務化されていますが、第三者機関による認証取得は任意です。
認証を受けることで、HACCPを実施・導入していることを取引先や消費者に周知でき、信頼性の向上が期待できます。また日本から食品を輸出する際、HACCP認証を要件とする国や地域もあります。
第三者機関による認証取得は、企業のブランド価値向上や輸出拡大につながる取り組みです。
8.HACCP導入に立ちはだかるさまざまなハードル

HACCPは、食品の安全性を維持するために効果的な衛生管理手法ですが、導入にあたっては多くの食品事業者が課題を抱えています。特によく見られる悩みは以下の通りです。
- 手書きによる記録作業の手間とミス
- 帳票の保管スペースの確保
- 多店舗展開による運用ルールのばらつき
- 人手不足による運用負荷
こうした課題を解決するには、デジタルツールの導入が効果的です。
サトーでは、HACCPで抱えがちな悩みを解決するソリューションをご提供しています。例えば温度記録の自動化やペーパーレス化など、効率的な衛生管理が実現可能です。
HACCPに関連するサトーのソリューションの詳細はこちらをご参照ください。
9.HACCP導入事例|株式会社ヤオコー様の取り組み

株式会社ヤオコー様では、物流センターにおける温度管理の精度向上を目的に、サトーの「HACCP CLOUD」を導入されました。
導入前は、物流センター各所で1日3回巡回による温度記録をしていましたが、人的ミスや帳票管理の煩雑さが課題となっていました。
「HACCP CLOUD」の導入後は、デジタル化によって人を介さないデータ取得を実現し、より強固な品質管理体制を確立されています。
【導入前の課題】
- 1日3回の温度記録は、即時の異常検知が難しく対応が困難だった
- 人手による温度記録は人的ミスが発生し管理精度が低かった
- 紙ベースの帳票ではデータの抽出が難しい
【導入による効果】
- 温度の常時自動取得で異常をいち早く察知、対応が可能に
- 巡回作業が不要に。人的ミスと人手不足を同時に解決
- データ分析が可能となり、強固な品質管理体制を確立
導入事例の詳細は以下をご確認ください。
10.全体で効率的な衛生管理を行うことが大切
HACCPは食品の安全性を維持するための効果的な衛生管理手法です。現場での運用を効率化し、継続的に改善していくことが求められます。
効率的な運用を行うには、デジタルツールを活用した記録の作成の自動化や、多拠点間でのルールの統一化・一元管理などが有効です。
サトーでは、データ収集と記録を自動化しペーパーレスで管理してHACCPに基づく食品衛生管理業務を支援するソリューションを提供しています。HACCP導入やシステム化に関するお悩みがある場合は、お気軽にサトーへご相談ください。
関連コンテンツ
商品やソリューションについてのお問い合わせ
受付時間24時間365日







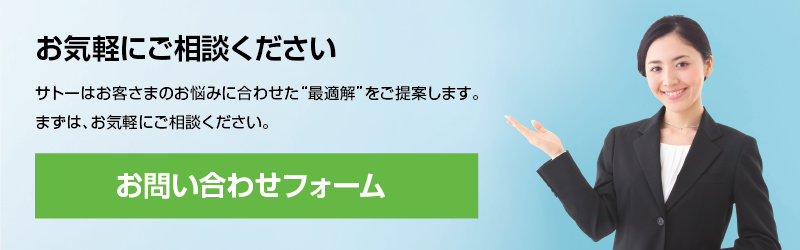












 サトークイックオーダー
サトークイックオーダー